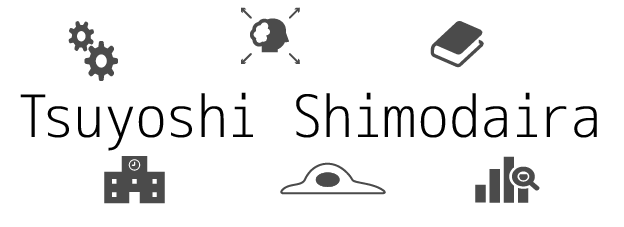研究における興味
- “人間らしさ” とは何か?
- “人間らしさ” のもとでどのような社会が形づくられるか?
- “人間が形作る社会” である以上,逃れらない社会のあり方とはどのようなものか?
大学学部生の頃に人間と社会の関係性について考えることがあったのですが,「個々の人間の集まりとして社会が形成されているけど,社会からも個々の人間は影響を受けているよな」とか「現に今こうして考えている自分自身の思考も社会的な環境の影響を受けてしまっているし,その枠組みの中で人間と社会の関係性について思考実験を重ねるのはどうなんだろうか」みたいなことを考えていました.その中で「人間が生物であるという,絶対に逃れることのできない制約条件のことを考えるべきなのでは?」「人間が逃れることのできない生物的な性質・側面によってどのような社会が形づくられ,逆にそのような社会から人間はどのような制約を受けているのだろうか?」というアイデアに思い至り,おそらく,これが今の自分の興味・関心に繋がる最初のきっかけでした.
それから生物としての “人間らしさ” や, “人間らしさ” と社会の関係性への興味を持つようになるのですが,当時,科学リテラシーのような教育について考えていたこともあり「”人間らしさ” から生まれる社会に “叛逆” するような教育目標や社会規範って実現不可能だよな」とも思うようになりました.だからこそ,”人間らしさ” と社会の関係性を明らかにすることは,今でいうWell-beingのような,人間が善く生きることやそれを実現する社会の実現に貢献することに繋がるのではないかと思うようになりました.
研究へのスタンス
自分の研究におけるスタンスとしては,大きく次の2つになるのかなと思います.
- 研究テーマや問いへのアプローチは分野に拘らずあらゆる方法・手段を考えて良い
- 研究することを社会から許されているのだから,その価値は社会に還元する必要がある
1つ目については,学部・修士の頃から多様な学問分野に触れていたことや,人と社会の関係性のような自身が興味を持っている事柄には多様な形で研究をしている人を知れたことなどが影響していると思います.実際に自分でもいろいろな研究アプローチを試してみて,自分の問いは1つのアプローチだけで完結する類のものでもなく,複数のアプローチを組み合わせながら “立体的な” 人間観/硏究観を構築していくことが大事だろうと思うようになりました.
自分の研究業績は,このスタンスを端的に表していると思います.
身近な先輩[安藤悠太さんや谷川嘉浩さんなど]の影響も大きかったと思います.
2つ目は,自分が一度研究のキャリアから離れたことから強く思うようになったことです.少し昔話をすると,自分は修士課程を修了した後に,直接博士課程に進学することができず,一度就職しています.就職していた頃はシチズンサイエンティストとして,仕事以外のプライベートのお金・時間を割きながら研究をしていました.その中で科学文化や科学教育に関する理論的な研究をなんとか試行錯誤しながら取り組んでいたのですが,仕事が終わった後のわずかな時間で自腹を切りながら研究していくことには少なからず厳しさもありました.当時と比べて,博士課程の学生として研究に集中することのできる環境にすごくありがたみを感じるものです(当時の研究体験は資料論文として公開しています).
こういうこともあって,谷川さんと話していた中で言っておられた「研究者って社会の中でみんなの代わりに考えることが許されている存在だよね」という言葉が身に沁みて感じたわけです(本人が覚えておられるかは分かりませんが笑).働きながら “考える” ってすごいエネルギーを使うって実感がありましたし,研究者という職業はお金をもらってみんなの代わりに “考える” 仕事なんだと思うようになりました.だからこそ,研究ができるありがたみはもちろん,研究の価値をどのように社会(みんな)に還元するかを意識するようになりました.
今は,研究成果から浮かび上がる人間の進化的起源の可能性を共有することを通して,私たち人間の先祖たちに想いを馳せるような,そんなロマンを共有することでみんなの心を少しでも豊かにすることができれば,と思いながら研究しています.
「教育」への考え方
「学校の先生になろうかな」と考えていたくらいには,昔から教育には興味がありましたし,教育に関する活動には社会活動として度々関わっています.ただ,自分が目指す教育への関わり方は,学校の先生や教員養成のようなものとは少し違うものになるだろうと感じています.
教育という営みや人間がもつ生物らしさに魅せられ,そして数理生物学という理論研究に魅せられた人間として,その立場だからこそ描き出すことのできる「教育」と人や社会の関係性の姿があると信じています.今私たちが見ている教育現象の性質が1つでも数理モデルという理論基盤のもとで説明することができるようになれば,それはより良い教育の実現に向けた確かな一歩になるはずです.そして,理論研究の立場から,安藤寿康先生の言うところの『進化教育学』のような分野・領域の構築を目指していくというのが,自分だから「教育」において果たすことのできる役割なのではないかという想いがあります.
その全体像がどのようなものになっていくのかはまだまだ見出せていませんが,一歩ずつ研究を積み重ねていきたいと考えています.